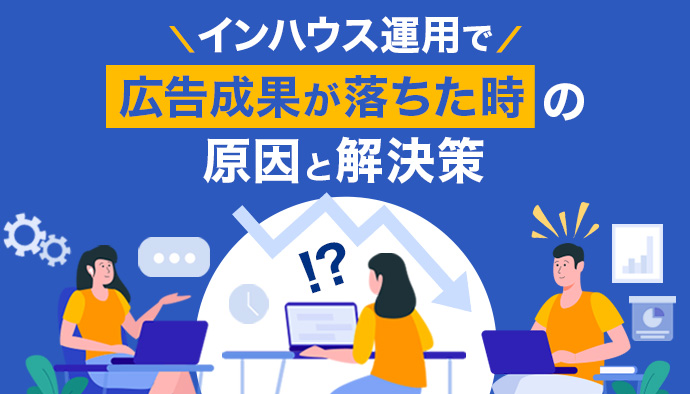
インハウスでWeb広告を運用しているものの、
思うように成果が上がらず悩んでいる担当者の方は多いのではないでしょうか?
「先月までは順調だった広告の成果が急に落ちてしまった」
「以前は効率よくコンバージョンを獲得できていたのに、最近は高騰している」
こんな状況に心当たりがある方は、運用のどこかに原因があるはずです。
本記事では、
インハウス運用で成果が低下する代表的な原因を整理し、すぐに実践できる改善策を
解説します。
1. インハウス運用で広告の成果が落ちる原因

インハウスでWeb広告を運用する際に成果が思うように上がらない背景として、
よく挙げられるのが「時間不足」と「知識不足」の2つです。
これらの問題は単独で発生することもあれば、相互に影響し合うこともあります。
まずは、
それぞれの原因がどのように広告運用に影響を与えるのかを具体的に見ていきましょう。
1-1. 原因①「時間不足」がもたらす運用品質への影響
インハウス運用で課題となりやすいのが、
他業務との兼務や、専任スタッフ不足による慢性的な時間不足です。
広告運用には、
日々のデータ分析、キーワードの最適化、クリエイティブの制作・更新、入札調整など、
さまざまな業務があります。
これらの作業が少数のスタッフ、場合によっては1人の担当者に集中していると、
どうしても作業が表面的になりやすくなります。
時間が十分に確保できない状態が続くと、
本来定期的に確認すべき検索語句レポートや除外キーワードの設定が後回しになり、
広告費の効率が下がる可能性があります。
また、
広告文やクリエイティブの更新頻度が低くなることで、
ユーザーの関心を維持するのが難しくなることも考えられます。
さらに、
Web広告業界の変化についていくのが難しくなる点も課題です。
新機能のリリースや仕様変更は頻繁に起こりますが、
時間が足りない状況では最新情報のキャッチアップが滞り、
他社との情報格差が広がることもあります。
1-2. 原因②「知識不足」が引き起こす判断のズレ
インハウス運用では、
代理店のような外部の専門知識が入りにくいため、
知識不足による判断のズレが運用に影響することがあります。
特に注意したいのは、
自動入札やターゲティング、トラッキングなど、
広告運用の基盤となる機能への理解不足です。
これらの機能を「難しそう」「設定が複雑」といった理由で十分に活用できない場合、
広告のポテンシャルを十分に引き出せないことがあります。
また、
過去の経験や成功事例に固執することも、知識不足の一つの現れです。
以前は効果的だった手法も、プラットフォームの仕様変更やユーザー行動の変化により、
現在では最適とは言えない可能性があります。
知識が十分でない状態では、
判断の基準が曖昧になり、管理画面の表面的な指標に振り回されやすくなります。
例えば、
品質スコアや最適化スコアの数値改善に注力するあまり、
本来の目的であるコンバージョンの獲得が十分に意識されないケースなどです。
1-3. 2つの原因が重なる場合のリスク
「時間不足」と「知識不足」が同時に起こる状況は、
インハウス運用において特に注意が必要です。
時間が足りないと新しい知識を学ぶ余裕がなくなり、
知識が不足しているため効率的な作業方法を見つけにくくなります。
その結果、
さらに時間が不足するという悪循環に陥ってしまいます。
このような状況では、
広告媒体のサポート担当者からの提案を十分に検討できなかったり、
「AIに任せれば安心」と考えて運用チェックを後回しにしてしまったりするケースもあります。
運用の質を維持し成果を伸ばすためには、
この悪循環を意識しつつ、計画的に学習や改善の時間を確保することが重要です。
2. 成果低下を招くNGパターンと改善策
 「時間不足」と「知識不足」は、
「時間不足」と「知識不足」は、
広告運用においてさまざまな課題を引き起こす要因となります。
これらが重なると効率が下がり、成果にも悪影響を及ぼしかねません。
まずは、
どのような問題が生じやすいのかを知ることが大切です。
具体的なパターンを把握すれば、
自社の運用状況を客観的に見直し、
改善すべきポイントを発見するきっかけになります。
以下に、
広告運用でよく見られるNGパターンをまとめました。
2-1. 時間不足が引き起こすNGパターン
■ 無駄なキーワードやターゲティングの放置
検索語句レポートを定期的に確認できないと、
コンバージョンに繋がりにくい検索語句への広告配信が続くことがあります。
結果として、
広告予算が効率的に使われず、CPAが高騰する可能性があります。
■ 広告文やクリエイティブの長期間未更新
同じクリエイティブを数ヶ月間配信し続けると、ユーザーに「広告疲れ」を起こさせ、
クリック率やコンバージョン率の低下につながりやすくなります。
たとえ長期間成果の良いクリエイティブがあったとしても、
別のパターンを試すなどして摩耗を防ぐ工夫が大切です。
■ 表面的な表面的な調整作業の繰り返し
キーワード追加や入札単価の微調整といった慣れた作業ばかりに時間を割いてしまうと、
根本的な改善にはつながりにくくなります。
定期的にデータ分析やターゲットの見直しを行い、
戦略的な改善につなげましょう。
2-2. 知識不足が引き起こすNGパターン
■ 予算の確保不足
そもそも広告運用に必要な予算が十分でない場合、
十分なデータが蓄積されず、機械学習の効果も十分に発揮されないことがあります。
目標の獲得件数や現実的なCPAをもとに、必要な広告予算を逆算して算出しましょう。
■ 過去の経験への固執
「手動入札の方が安全」「完全一致キーワードが望ましい」といった判断に固執すると、
プラットフォームの進化やユーザー行動の変化を考慮できず、
改善の機会を逃す可能性があります。
過去の成功事例に依存せず、
最新のデータやプラットフォームの仕様に適した運用を心がけ、
小さなテストを繰り返してPDCAサイクルを回す習慣を持ちましょう。
■ 管理画面の指標への過度な依存
品質スコアや最適化スコアの改善に注力するあまり、
実際のコンバージョン数やCPAなど本質的な成果指標が軽視されることがあります。
例えば、
CPAを改善したい場合は、クリック単価やコンバージョン率など、
直接的に影響する指標の改善に注力することが効果的です。
このように、
何を改善したいのかを明確にし、それに対応する指標を意識することが重要です。
■ 細かすぎる管理・調整
キャンペーンや広告グループの過度な細分化やターゲティング条件の狭めすぎは、
機械学習の効果を阻害する場合があります。
キャンペーン構造やターゲティングは必要最小限に整理し、
機械学習が十分に学習できる環境を整えることが重要です。
■ ランディングページ最適化の不足
広告でユーザーを集めても、
遷移先ページが最適化されていないと、コンバージョン率の向上が難しくなります。
ランディングページの内容や広告流入(キーワードや広告文など)からの導線を見直し、
ABテストを通じて改善を図りましょう。
2-3. 複合的な問題が引き起こすNGパターン
■ 提案の安易な実装
広告媒体のサポート担当者からの提案を十分に検討せずに実装すると、
自社の状況や目標に適さない施策が混ざる可能性があります。
その結果、
期待した成果が得られないどころか、
場合によっては広告費の非効率な消費につながることもあります。
提案を活用する際は、
自社のデータや運用方針と照らし合わせ、必要に応じて調整することが重要です。
■ AIへの過度な期待
「AIに任せれば成果が出る」と考えて運用を放置すると、
機械学習は万能ではないため、期待通りの結果にならない可能性があります。
適切な目標設定や継続的な監視・調整が重要です。
3. インハウス運用で成果を出す解決策

インハウス運用で安定した成果を出すためには、
根本的な原因である「時間不足」と「知識不足」それぞれに対する
具体的な対策を講じることが重要です。
3-1. 時間不足に対する解決策
まず、
運用体制の整備が不可欠です。
広告運用業務の優先順位を明確にし、
重要度の高い作業に十分な時間を割り当てられる体制を構築しましょう。
可能であれば専任担当者を配置し、
他業務との兼務による負荷を最小限に抑えることが理想的です。
定期的な情報収集の時間を確保することも重要です。
月に1回程度でも、
業界の最新動向や新機能に関する情報をチェックする時間を設けることで、
競合他社との情報格差を縮め、運用判断の精度向上につなげることができます。
また、
作業の効率化も検討しましょう。
レポート作成の自動化や、繰り返し作業のテンプレート化により、
本質的な分析や戦略立案により多くの時間を割けるようになります。
こうした工夫を組み合わせることで、
時間不足による運用課題の影響を軽減できます。
3-2. 知識不足に対する解決策
知識習得のためには、
まず信頼できる情報源を特定することが大切です。
各広告媒体の公式ヘルプページや、
実績のある代理店が発信するブログ・記事を定期的にチェックし、
正確な情報を効率的に入手する習慣を身につけましょう。
社内での情報共有体制の構築も効果的です。
運用担当者が複数いる場合は、定期的に情報交換の場を設け、
個々の経験や知識を組織全体で共有できる仕組みを作ることが望ましいです。
こうすることで、
属人的になりがちな知識をチーム全体の資産として活用できます。
さらに、
外部の専門家との接点を持つことも重要です。
セミナーやウェビナー、業界コミュニティへの参加を通じて、
最新のトレンドや成功事例を学ぶ機会を積極的に作ることで、
運用判断の幅や精度を高めることができます。
3-3. 継続的な成果向上のための取り組み
長期的に成果を向上させるためには、
データに基づく意思決定の文化を社内に根付かせることが欠かせません。
感覚や経験だけに頼らず、
必ず数値を確認してから施策の実施や継続を判断する習慣を身につけましょう。
また、
小さな改善の積み重ねを重視し、一度に大幅な変更は避けることが重要です。
一度に多くの変更を加えると、どの施策が効果的だったかを判断しにくくなります。
施策は一つずつ検証を重ね、
確実に成果につながる改善を見極めながら運用を進めることが大切です。
4. まとめ
インハウス広告運用で成果が落ちる根本原因は、
「時間不足」と「知識不足」の2つに集約されます。
これらの問題を放置すると、
無駄な予算消費や機会損失など、さまざまなNGパターンに陥る可能性があります。
しかし、
適切な運用体制の整備や継続的な学習を行うことで、こうした課題は改善が可能です。
まずは自社の現状を客観的に分析し、
優先度の高い課題から順に対策を講じていくことが重要です。
インハウス運用の最大の強みは、
迅速な意思決定と施策実行にあります。
この記事で紹介したポイントを参考に、
自社に合った運用ノウハウを蓄積し、
持続的に広告成果を向上させる取り組みを進めていきましょう。
※本記事は当社の広告運用の知見に基づくものであり、効果や成果を保証するものではありません。

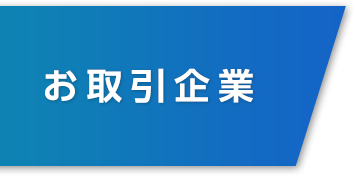
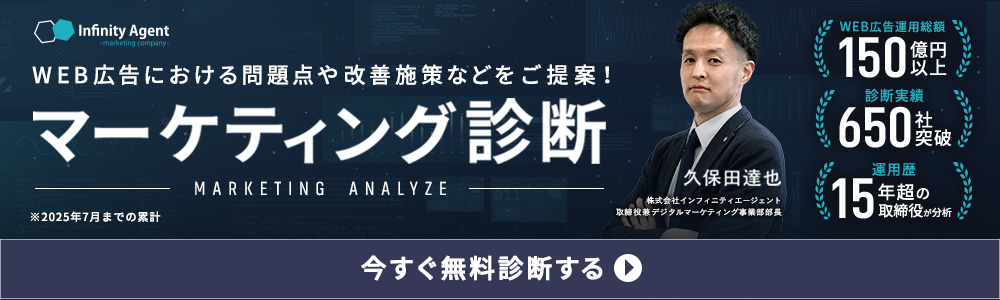







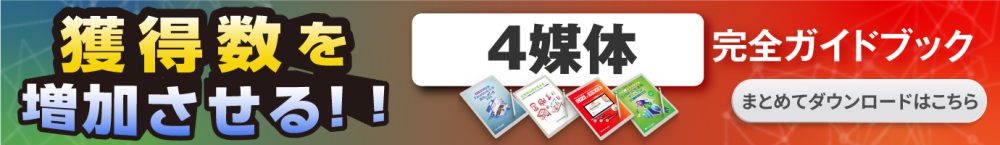
















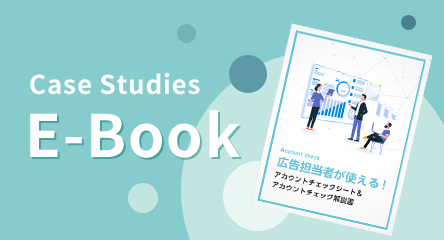 無料E-Bookダウンロード
無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断
無料マーケティング診断 お問い合わせ
お問い合わせ