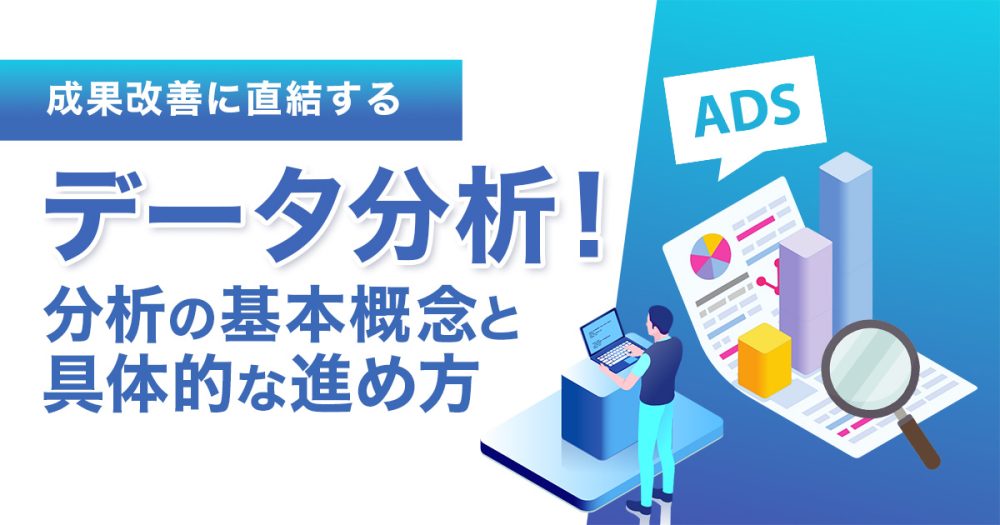
WEB広告を運用するうえでは「出稿して終わり」ではなく、
効果測定とデータ分析を通じて成果を最大化することが重要です。
WEB広告ではすべてのデータが数値で可視化出来るため、
適切な分析を行えば、どの施策が効果的で、
どこに改善の余地があるのかを明確にすることができます。
本記事では、
WEB広告分析の重要性と3つの基本原則を解説し、
実際に改善分析を行う際のポイントを詳しくご紹介します。
1. WEB広告の分析が重要な理由
WEB広告の大きなメリットは、
すべての指標が数値として可視化されることです。
クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、広告費用対効果(ROAS)など、
多くの指標を分析することで、施策の良し悪しを判断できます。
裏を返せば、
WEB広告はデータ分析無しでは効果を最大化させることはできません。
また、
WEB広告を分析をする際は、
感覚ではなくデータに基づいた判断が必要不可欠です。
例えば
「この広告はデザインがかっこいいから成果が出るはず」
といった主観的な予測ではなく、数値を見て
「この広告はクリック率が低いけどコンバージョン率が良いので、
訴求は変えずクリック率が高い広告のデザインに変更しよう」
といった具体的な改善策が立てられます。

データ分析を行い、効果の低い広告やターゲティングを見直し、
成果の高い施策に予算を集中させることで、
限られた広告費を最大限に活用できます。
さらに、
競争の激しい市場では、
競合他社の動向や業界の平均値と比較しながら戦略を最適化することで、
より有利なポジションを築くことが可能になります。
このように、
WEB広告のデータ分析を適切に行うことで、費用対効果を最大化させ、
競争が激しい市場でも効率的にシェアを拡大できるのです。
では、
具体的にどのような分析手法を用いればいいのか、
マスターするべき3つの方法を解説します。
2. WEB広告分析の基本原則
WEB広告分析の基本は、
「比較」「ドリルダウン」「カテゴライズ」の3つの視点です。
この3つを意識することで現状の課題を正しく特定し、
適切な改善策を打ち出すことができます。
2-1.分析の基本は「比較」
まず、何よりも基本になることが
「比較」を行うことです。
比較をすることで、
効果が良かったときと何が変化したのか・どこに問題があるのか
を明確にすることができます。

では、
何を比較したらいいのか、代表的な手法をご紹介します。
■ 期間で比較する
前月や前年同月と比較して、どの指標が悪化しているのかを明確にします。
これを行うことで、
クリック率なのか、コンバージョン率なのか等
どの指標に焦点を当てて施策を打ち出していくのかの方向性が定まります。
■ ABテストで比較する
クリエイティブやターゲティングについては、
特にこの比較手法がポイントになります。
クリエイティブについては、
訴求は同じでもデザインを変えることでクリック率が大きく変化することがあります。
効果の高いデザインが把握できれば訴求を変えての検証や、
寒色か暖色か、イラストか写真か等の展開がしやすくなり、
効果検証のPDCAを高速に回せるようになります。
勝ちパターンを見つけていくためにも比較検証は重要です。
■ 他社や業界平均との比較
他社と比較することで、
要因があると仮定している指標が客観的に見て良いのか悪いのかが明確になります。
クリック率が他社と比較して低い場合、
訴求に課題があるのか他社との特典等のオファーに差があるのかなどを考えることもできますし、
反対に過去と比較して効率が高い状況でも、
業界で見ると平均的でまだ伸ばせる見込みがあるなどの視点も持つことができます。
つまり
「比較」は改善ポイントを見つけるための最も基本の方法と言えます。
2-2. 大きなデータからドリルダウンしてみること
WEB広告のデータ分析は、
いきなりターゲット属性やクリエイティブ等、細かい単位を見てはいけません。
たとえその部分の成果が悪く改善施策を打ったとしても、
運用しているWEB広告全体で見ればほんの些細な違いにしかならない可能性があります。
全体へのインパクトが大きい部分を見極め、
改善施策を打つことで効果の高い広告運用が実現できるのです。
つまり、
全体の傾向を把握したあとに、
より細かい単位で深掘りして問題を特定することが重要になります。
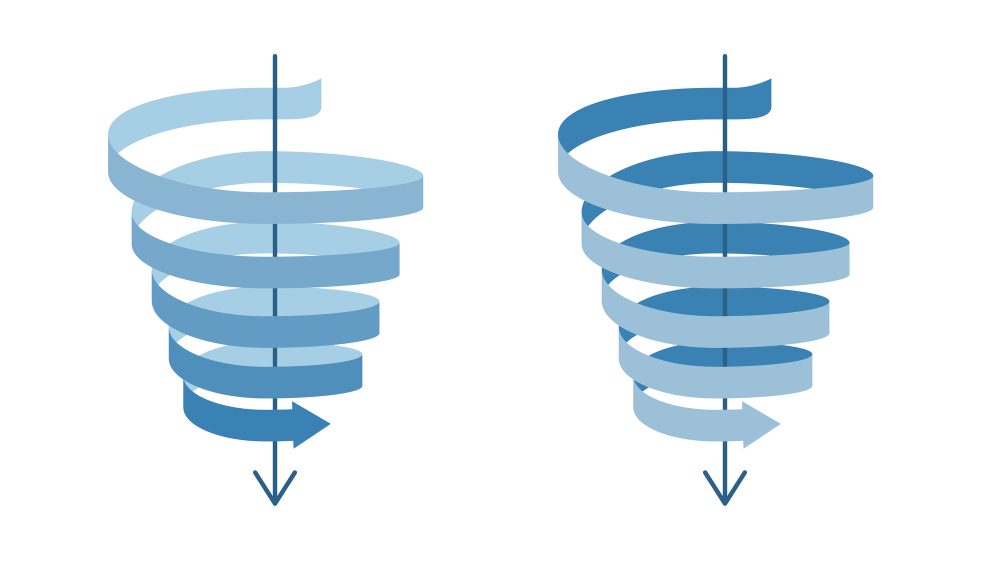
■ ドリルダウンの手順
①全体のデータを確認する。
(例:月を追うごとにコンバージョン率が低下している。)
②配信メニューや媒体ごとのデータを確認する。
(例:特に配信割合が多い検索広告が低下しており、中でもGoogleでの低下が目立っている。)
③キーワード/オーディエンス等の細かい単位で確認する。
(例:特定の軸キーワードのコンバージョン率が極端に低いが、
3月を追うごとに配信割合が上がっている。)
④改善施策を打つ。
(例:キーワードの入札を抑える、除外を検討する。)
このように、
最初は広い視点で全体像をおさえ、問題のある部分を特定し、
そこをさらに深堀りして細かく分析していくことが重要です。
2-3. カテゴライズ分析で傾向を確認
カテゴライズ分析とは、
異なるデータを「分類」することで特定の傾向をつかむ分析方法です。
先にお伝えしたように、
WEB広告はすべての指標を数値として可視化することができます。
ここで広告運用者がぶつかることが多い課題が
「情報が多すぎる」ということです。
しかし、
一見膨大に思えるデータの中にも傾向は存在します。
その傾向をつかむために行うのが
「カテゴライズ分析」です。

例えば、
人材サービスについて検索広告を運用していたとき、
実際に検索されているワードを1つ1つ分析することは不可能に近いです。
ただ、そのワードが「給与」に関することなのか、
「福利厚生」なのか「地域」なのか等、
分類をすることでどのキーワード群が良いのか判断がつきやすくなります。
その他にもカテゴライズの例はこのようなものがあります。
■ キーワードを分類する
検索広告のキーワードを
「指名(サービスの固有名称)」か「一般(サービスのカテゴリ)」に分類
一般キーワードの中でもさらに細かな粒度で深堀する
(例:〇〇を含む含まない、エリア名ありなし等)
■ 配信先(プレースメント)を分類する
ディスプレイ広告や動画広告などが配信された配信先(プレースメント)を
「ニュース系サイト」か「趣味系のブログ」等で分類
■ ターゲット層を分類する
「20代男性」か「30代男性」、「公務員」か「営業職」等
膨大なデータでも適切に分類することで、
どの部分に施策を打ち最適化をかけていくのかを明確にすることができるのです。
3. まとめ
いかがでしたでしょうか?
WEB広告を運用するうえでは、
効果測定とデータ分析を通じて成果を最大化することが重要です。
今回は、効果的な改善分析を行うためにマスターするべき3つの原則を解説しました。
- 比較を行い、変化や問題点を特定する
- 大きなデータからドリルダウンし、詳細に分析する
- データをカテゴライズして、傾向を把握する
これらの分析フローを確立することで、
感覚ではなくデータに基づいた納得感のある施策を打ち出し、
広告の効果を最大化することができます。
今回のポイントを参考に、WEB広告を改善に導ける広告運用者を目指しましょう。

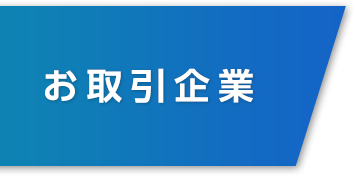
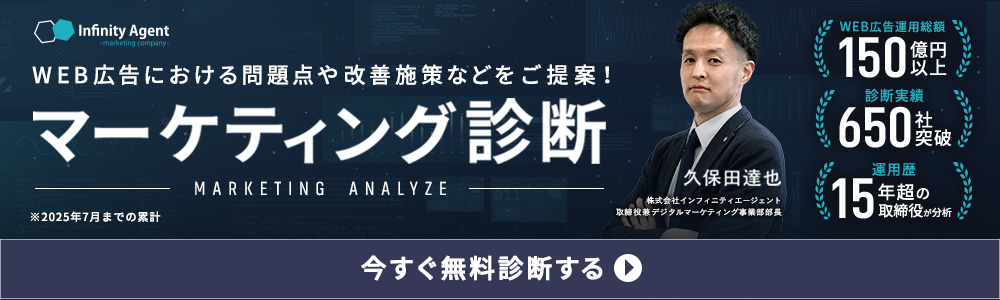







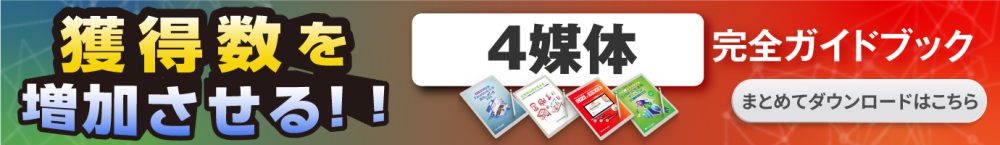


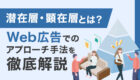













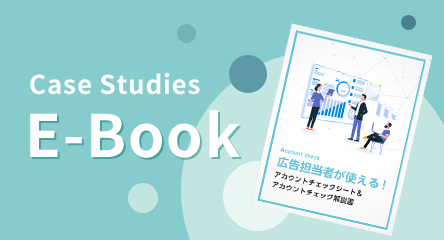 無料E-Bookダウンロード
無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断
無料マーケティング診断 お問い合わせ
お問い合わせ