
Web広告は、
低予算から認知拡大や購買促進を目指せる効果的なマーケティング手法です。
しかし、
成果を出すためには媒体や分析について専門的な知識が必要になるため、
内製化を進めるべきなのか悩む人もいるでしょう。
本記事では、
Web広告の内製化を検討する要因や実行するメリットなどを解説していきます。
ポイントについて紹介するので、
内製化をするべきなのか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
1. そもそもWeb広告の内製化とは
2. 代理店からWeb広告の内製化を検討する要因
2-1. 代理店とのコミュニケーションに問題がある
2-2. 代理店のPDCAのスピード感が悪い
2-3. 運用にコストがかかりすぎている
2-4. 社内に広告運用の知識が溜まらない
3. Web広告で代理店に不満を抱えてしまう理由
3-1. 新人が担当になるケースがある
3-2. 得意な媒体や業種が異なる
3-3. 最新情報やトレンドへの対応が遅い
4. Web広告の内製化で得られるメリット
4-1. 社内にノウハウを溜められる
4-2. 外注コストを削減できる
4-3. サービスについて熟知した人物が担当できる
4-4. 状況に応じた運用が可能になる
4-5. ブランドイメージの一貫性を保ちやすい
5. Web広告の内製化によるデメリット
5-1. 新しい情報を常にアップデートする必要がある
5-2. 運用者の育成や発掘が必須になる
5-3. ノウハウが担当者によって偏る可能性がある
5-4. 専門ツールの導入コストがかかる場合がある
5-5. リスク管理と法規制への対応が必要になる
6. Web広告を内製化させるためのポイント
6-1. 内製化を支援してくれるサービスを導入する
6-2. 運用体制を構築して専門的なチームを作る
7. まとめ
1. そもそもWeb広告の内製化とは

そもそもWeb広告の内製化とは、
自社内で広告運用を完結させることです。
広告を配信する場合は大きく分けて、
以下の2つの手法が考えられます。
- 代理店に頼む手法:アウトソーシング
- 社内で実行する手法:インハウス
アウトソーシングでは、
専門的な知識を持った担当者に運用を任せて、他の業務に集中することが可能です。
インハウスでは、
社内に知識を蓄積しながら細かな運用調整が可能です。
アカウント開設から広告クリエイティブの制作・運用レポート作成・効果測定まで
多岐にわたる業務が発生します。
アウトソーシングとインハウス、
それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
特に、Web広告インハウス化を検討する際には、
必要なリソースと得られる効果を綿密に比較検討する必要があります。
2. 代理店からWeb広告の内製化を検討する要因
代理店を活用している場合、
以下の理由から内製化を検討することが多いです。
- 代理店とのコミュニケーションに問題がある
- 代理店のPDCAのスピード感が悪い
- 運用にコストがかかりすぎている
- 社内に広告運用の知識が溜まらない
自社に当てはまっている項目がないか確認してみましょう。
2-1. 代理店とのコミュニケーションに問題がある
代理店とのコミュニケーションに問題がある場合、
Web広告の内製化を検討するケースが多いです。
例えば広告運用についての改善案について、
「良い提案をもらえなかった」
「細かい調整でも対応まで数時間、あるいは数日かかってしまった」など、
事例が挙げられます。
担当者の変更や指摘などを行っても状況が変わらないのであれば、
内製化について検討した方が良いでしょう。
2-2. 代理店のPDCAのスピード感が悪い
広告で成果を出すためには、
リアルタイムの成果を確認しながらPDCAを高速で回すことが不可欠です。
特に、以下の指標は、迅速なチェックが必要です。
- 広告のクリック率(CTR)
- コンバージョン率(CVR)
- 費用対効果(ROAS / ROI)
代理店の対応が遅い場合、機会損失につながる可能性があります。
さらに、
広告アカウントへのアクセス権が共有されず、運用状況がブラックボックス化している場合は、
迅速な状況把握や改善提案が困難になります。
Web広告の内製化を真剣に検討するべきでしょう。
2-3. 運用にコストがかかりすぎている
広告の内製化を検討する要因として、
運用にコストがかかりすぎているケースも考えられます。
対応しているサービス内容に対してコストが見合っていないと感じる場合は、
自社運用に切り替えることも検討した方が良いでしょう。
中には代理店の対応に問題はないものの、
予算の縮小によって仕方なく運用方法を切り替えることもあります。
2-4. 社内に広告運用の知識が溜まらない
代理店は、
媒体や分析についての深い知識を持っているため、
運用を任せることで短期間の成果につながりやすいです。
しかし、
外部に依存しすぎると社内に運用の知識やノウハウが溜まらないこともあります。
特に、
“広告アカウントが代理店名義で制作されている場合”
“効果測定ツールとの連携が不十分な場合”
などは注意が必要です。
契約終了後にスムーズな引き継ぎが行えず、
自社で一からノウハウを構築し直す必要が生じる可能性があります。
将来的な広告運用内製化を見据えるのであれば、
代理店任せにせず、アカウント構造や主要な指標・改善の考え方など、
ある程度の知識を社内でも蓄積しておくことを強く推奨します。
3. Web広告で代理店に不満を抱えてしまう理由

Web広告で代理店に不満を抱えてしまう理由としては、
以下3つのことが挙げられます。
- 新人が担当になるケースがある
- 得意な媒体や業種が異なる
- 最新情報やトレンドへの対応が遅い
それぞれ解説していきます。
3-1. 新人が担当になるケースがある
一般的に、
広告費用によって以下のように、担当者が変わることもあります。
- 多額な場合:経験を積んだ担当者
- 少額の場合:新人が担当者
新人の場合、
知識やビジネスコミュニケーションスキルが追いついていないため、
ストレスを感じる可能性が高いです。
広告費用によっては変更に応じてもらえないこともあるので、
どのような人物が担当になるのか事前に確認しておいた方が良いでしょう。
3-2. 得意な媒体や業種が異なる
Web広告を配信できる媒体は、
各種SNSやGoogle・Yahoo!などさまざまな種類が存在します。
美容や転職など業種によっても適切な媒体は変わるので、
代理店が得意な分野について事前に確認しておくことが大切です。
「BtoCとBtoBのどちらが得意なのか」など、
具体的な実績をもとにしてから代理店を選択してください。
3-3. 最新情報やトレンドへの対応が遅い
代理店は多くのクライアントを抱えているため、
以下の3つのようなトレンドへのキャッチアップが遅れるケースがあります。
- 特定の業界や媒体における最新情報
- GoogleやMetaなどのプラットフォームのアルゴリズム変更
- 新しい広告フォーマットの登場
常に変化するWeb広告の環境において、この遅れは成果に直結します。
自社で迅速に情報を収集し、
戦略に反映させたいと考える企業は内製化を検討する傾向にあります。
特に2025年現在、
「AIを活用した広告運用の最適化」
「プライバシー規制の強化(サードパーティCookieの廃止など)」
といった最新動向への対応は、企業のマーケティング戦略において極めて重要です。
4. Web広告の内製化で得られるメリット
Web広告の内製化では以下のようなメリットを得られます。
- 社内にノウハウを溜められる
- 外注コストを削減できる
- サービスについて熟知した人物が担当できる
- 状況に応じた運用が可能になる
- ブランドイメージの一貫性を保ちやすい
具体的な利点について確認していきましょう。
4-1. 社内にノウハウを溜められる
Web広告の内製化を進めることで、
社内にノウハウを蓄積することが可能です。
外部に依存することなく運用を進められるため、
市場のニーズや流行の変化などにも素早い対応が可能です。
商品ジャンルごとの傾向などもまとめやすくなるので、
貯めたノウハウを将来的な自社のマーケティング財産として活用できるようになるでしょう。
これは、
長期的な視点で企業の競争力を高める上で非常に大きなメリットとなります。
4-2. 外注コストを削減できる
代理店を活用するには、
手数料として広告費用の15%〜20%ほどを支払う必要があります。
■ 削減効果の例
広告費用 / 月:100万
広告費用 / 年:1200万
外注手数料 / 年(費用の15~20%):240万
内製化すると…
外注手数料分の予算を削減
⇓
「削減分を広告費に充てる」
「他のマーケティング活動に投資したりすること」
などが可能
無駄な費用が継続して消費されることもあるため、
サービスが手数料に見合っていないのであれば、
契約の見直しや内製化を検討することがおすすめです。
4-3. サービスについて熟知した人物が担当できる
社内の人材に広告運用を任せると、
自社サービスに精通した人物が状況判断を行うことが可能です。
「広告内に記載する商品情報やLP内の表現」
「ターゲットに響く細かな訴求ポイント」など、
自社の強みや顧客のインサイトを深く理解し調整を行うため、より高い成果を期待できます。
もちろん外部の方でも適切な訴求ポイントを把握することは可能ですが、
ターゲット層などにズレが生じている場合は理解度の高い社内の人員に任せてみましょう。
4-4. 状況に応じた運用が可能になる
内製化によって蓄積したノウハウを活用し、
マニュアル作成や人材の育成を行うことで、状況に応じた運用することが可能です。
代理店に依頼する場合は、
要望を伝えてから、実際に反映されるまで時間がかかるケースもあります。
一方、
社内であればスピーディーな対応が可能です。
「緊急性の高いキャンペーン」
「市場の変化に合わせた細かな調整が必要な場合」でも、
迅速にPDCAを回すことができるため、機会損失を最小限に抑えることが可能です。
代理店とのコミュニケーションコストが必要以上にかかっている場合も、
内製化で改善を目指していきましょう。
4-5. ブランドイメージの一貫性を保ちやすい
Web広告の内製化は、
ブランドイメージの一貫性を保つ上でも大きなメリットをもたらします。
代理店に依頼する場合、
広告クリエイティブやメッセージの方向性について、
細かなニュアンスが伝わりにくいことがあります。
しかし、自社で運用すれば、
ブランドガイドラインや企業理念を深く理解した担当者が直接広告を制作・運用するため、
一貫性のあるメッセージをユーザーに届けることが可能です。
これにより、
ブランド認知度の向上・顧客エンゲージメントの強化にもつながります。
5. Web広告の内製化によるデメリット
Web広告の内製化には、
以下のようなデメリットも存在します。
- 新しい情報を常にアップデートする必要がある
- 運用者の育成や発掘が必須になる
- ノウハウが担当者によって偏る可能性がある
- 専門ツールの導入コストがかかる場合がある
- リスク管理と法規制への対応が必要になる
利点だけでなく上記の課題やリスクについても把握しておきましょう。
5-1. 新しい情報を常にアップデートする必要がある
Web広告を配信する各媒体では、
提供するサービス内容や仕様が定期的に変更されます。
また、
商品へのニーズや流行も日々変わるため、情報収集が欠かせません。
代理店の場合は、
媒体のアップデートやニーズに敏感で、迅速な対応が可能です。
内製化するには自社で情報を集める必要があるため、
担当者の負担が大きくなることに注意しましょう。
特に、GoogleやMetaなどのアルゴリズム変更は頻繁に行われるため、
専門知識を持った担当者が常に最新情報をキャッチアップし続ける必要があります。
5-2. 運用者の育成や発掘が必須になる
自社に広告運用の経験者がいない場合は、
育成や発掘が必要です。
媒体によって利用するツールや改善で注目すべきポイントが異なるため、
一から育成・発掘を行うと予算や時間がかかることがあります。
十分な人材の確保が望めない際は、
代理店から知識を共有してもらい、半内製化から始めることがおすすめです。
5-3. ノウハウが担当者によって偏る可能性がある
内製化は、
自社内で知識を蓄積できるメリットがありますが、
ノウハウが担当者によって偏るリスクもあります。
ツールの使用方法や出稿時の細かい設定方法など、
作業が属人化してしまうと担当が変わったときなどに
成果が見込めなくなることもあるので注意が必要です。
後でトラブルが発生しないように、
事前にチームの体制を整えておきましょう。
5-4. 専門ツールの導入コストがかかる場合がある
Web広告運用を本格的に内製化する場合、
以下の専門的なツールの導入が必要になることがあります。
- 効果測定ツール
- A/Bテストツール
- 競合分析ツール
- 自動入札ツール
これらのツールは高機能である反面、
初期費用や月額費用がかかることが多いです。
運用コストの削減を目指して内製化しても、
ツール費用が意外な負担となるケースがあります。
導入前に、
「必要なツールの洗い出しと」
「それにかかるコストを正確に把握すること」
が重要です。
5-5. リスク管理と法規制への対応が必要になる
Web広告運用には、
景品表示法、薬機法、特定商取引法などの法規制が関わってきます。
また、
ユーザーのプライバシー保護に関する規制(GDPR、CCPAなど)も世界的に強化されており、
日本でも個人情報保護法が改正されるなど、
常に最新の情報をキャッチアップし、適切な対応をとる必要があります。
代理店であればこれらのリスク管理や法規制への対応を一任できますが、
内製化する場合は、自社でこれらの知識を習得し、
広告表現やデータ管理に細心の注意を払う責任が発生します。
専門家による法的レビューの体制を整えるなど、
リスクを最小限に抑えるための準備が不可欠です。
6. Web広告を内製化させるためのポイント

Web広告を内製化を成功させるための主なポイントは、
以下の2つが挙げられます。
- 内製化を支援してくれるサービスを導入する
- 運用体制を構築して専門的なチームを作る
実際に内製化する際に成果が見込めるように
上記もチェックしておきましょう。
6-1. 内製化を支援してくれるサービスを導入する
社内の内製化を進める際、
運用の知識がゼロだと無駄な時間や予算が消費されてしまうケースが多いです。
リスクが多いため、
外部が提供している内製化支援のサービスを取り入れることも視野に入れましょう。
支援サービスを活用すると、以下の内容などが可能になります。
- 自社独自の強み・弱みの客観的な分析
- 市場におけるポジショニングの把握
このように、
より戦略的な広告運用内製化が可能になります。
6-2. 運用体制を構築して専門的なチームを作る
社内で他の業務も担当しているメンバーに広告運用を任せると、
作業が多岐に渡り、どちらも中途半端になるリスクがあります。
担当者が広告運用に集中できるよう、
専門的なチームを組成し、役割分担を明確にすることが重要です。
また、
特定の担当者にノウハウが集中する属人化を防ぐため、
運用マニュアルの作成・定期的な情報共有会の実施・複数名でのレビュー体制の構築など、
業務が偏らないような仕組み作りも不可欠です。
これにより、
担当者の急な離脱時にも安定した運用を継続できるようになります。
7. まとめ
いかがでしたか?
Web広告の内製化は、
ノウハウの蓄積や外注コストの削減などさまざまなメリットがあります。
ノウハウの蓄積・外注コストの削減・迅速な意思決定・ブランドの一貫性維持など、
企業にとって計り知れないメリットをもたらします。
しかし、
新しい情報の継続的なアップデート・専門人材の育成・確保・ノウハウの属人化リスク・
専門ツールの導入コスト・法規制への対応といったデメリットも存在するため、
これらの課題を理解した上で慎重に検討を進めることが重要です。
もしゼロから完全な内製化を目指すのが難しいと感じる場合は、
まずは代理店と連携しながら段階的にノウハウを共有してもらう
「半内製化」から始めることを強くおすすめします。
自社のリソースと目標を明確にし、
最適な広告運用内製化の形を見つけていきましょう。

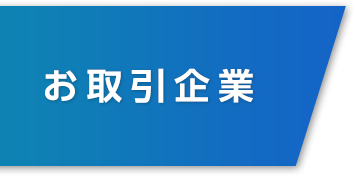
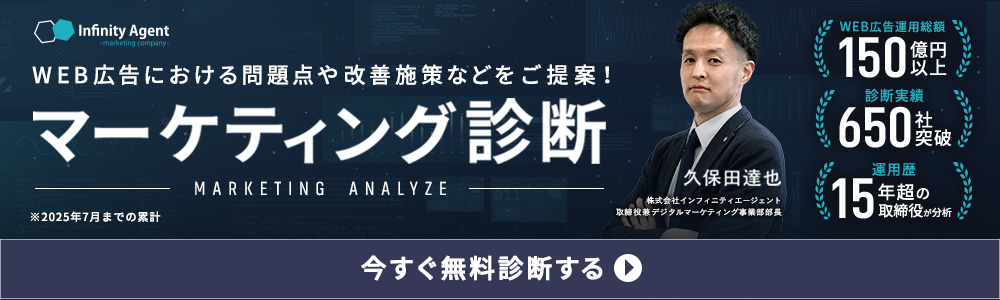







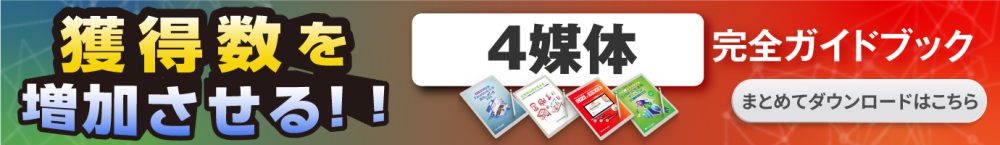





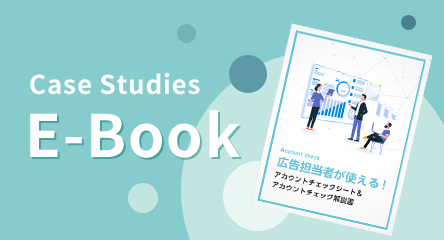 無料E-Bookダウンロード
無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断
無料マーケティング診断 お問い合わせ
お問い合わせ

