
Facebook広告を活用する際、なんとなく入札戦略を決めてしまうと、予算の消費がうまくいかない可能性が高まってしまいます。
パフォーマンスを最適化させるために、入札戦略で設定できる項目や選び方など理解を深めておくことが大切です。
この記事では、入札戦略についての概要や選択方法、メリット・デメリットなども合わせて解説していきます。
「どのように入札戦略を調整すれば良いの?」と疑問に思っている方はぜひ参考にしてみてください。
入札戦略とは?
入札戦略とは、広告配信の目的を達成するために予算を適切に消費するための設定項目です。
キャンペーンごとに最適な入札戦略を実施することで、費用対効果を高められます。
Facebook広告では、選択された入札戦略に合わせて自動で広告の入札価格を決定するため、事前の設定が重要です。
Facebook広告の入札戦略について
Facebook広告の入札戦略では、以下5つの種類が存在します。
・バリュー最大化
・結果の単価目標
・ROAS目標(広告費用対効果)
・入札価格上限
それぞれの内容について解説していきます。
最大数量
Facebook広告の最大数量は、設定された予算で最大の成果を出すことを目指す入札オプションです。
予算を使い切ることに重きを置いているため、イベントの開催など多くの顧客を獲得したい際は活用することが推奨されます。
ただし、最大数量ではCPAの最適化が実施されないので注意が必要です。
バリュー最大化
バリュー最大化は、設定された予算のうち、最も高額な購入になるように入札を実施します。
自社で複数の商品を扱っていて、可能な限り多くの購入を求めているものの、特に高単価な商品を販売促進したいときに設定がおすすめです。
結果の単価目標
結果の単価目標では、設定された目標金額を元に、システムがキャンペーン全体の平均金額を維持するように動きます。
また、結果を最大化させるために、ダイナミックな入札を実施してくれる点も特徴です。
例えば小売店などの場合、結果の目標単価で収益性が見込みやすい商品の購入単価を設定することが推奨されます。
ROAS目標(広告費用対効果)
ROASは「Return On Advertising Spend」の略称で、日本語だと広告による費用対効果を表します。
広告費用に対して、どの程度成果を得られたのかを表す数値で、広告配信では重要指標の1つです。
FacebookのROAS目標では、事前に設定した目標を達成するように、システムがキャンペーン期間の配信を調整します。
「結果の単価目標」と同様に、結果を最大化するためにダイナミックな配信を行うこともメリットです。
ただし「結果の単価目標」とは違って、ROAS目標では予算金額の消化は保証されません。
入札価格上限
入札価格上限では、オークション別に入札価格の上限を設定して配信します。
指定された金額よりも、クリック単価やインプレッション単価などが低くなるように入札されることが特徴です。
入札価格上限は、予測コンバージョン率について理解して、最適な入札価格を算出できる広告主が対象とされています。
入札戦略の選び方
入札戦略を選ぶ際は、自社の目標などを考慮しながら最適なものを選択しましょう。
初心者であれば、広告の費用を最大限活用しながら配信する最大数量がおすすめです。
運用について知識があり、広告による購入金額を詳細に管理したい場合は、ROAS目標を検討してみてください。
また、内部入札・LTVモデルを活用する広告主には、入札価格上限の導入が推奨されます。
入札戦略のメリット
入札戦略のメリットは以下の3つです。
・広告費の削減につながる
・効率的な目標達成を実現できる
どのような利点があるのか詳しく見ていきましょう。
運用の手間を削減できる
入札戦略を活用するメリットとして特に大きいのが、運用の手間を削減できる点です。
Facebook広告では、自動入札を選択することで人的なリソースを確保する必要がなくなります。
機械学習によって手動で適宜調整を行うよりも効果的な配信が実現できるため、金銭的なコストや時間の面で大きな削減につながるでしょう。
広告費の削減につながる
入札戦略では、広告が表示されるたびに、システムによって入札単価を適宜調整します。
手動で調整するよりも高頻度で調整できるので、必要のない広告費を削減することにもつながるでしょう。
無駄な費用を減らすことができれば、さらに最大のパフォーマンスを発揮しやすくなります。
効率的な目標達成を実現できる
Facebook広告の入札戦略を設定することで、目標達成の効率的な実現もできます。
AIの自動学習によって適切なユーザーを判別し、広告を配信することが可能であるため、よりコンバージョンが見込める顧客を対象にしやすい点が魅力だといえるでしょう。
自身で予算の操作を行う場合は、過去の配信履歴から傾向を掴み、キーワードや配信枠ごとの単価を見極めなければいけません。
Facebookの膨大なデータを用いて自動的に判断を下してくれるため、目標達成の効率化が実現できます。
入札戦略のデメリット
入札戦略には、以下2つのようなデメリットもあります。
・データを集めるのに一定の期間が必要になる
メリットと合わせて、上記についても内容を把握しておきましょう。
予算を消費しきれない可能性がある
入札戦略によっては、Facebook内で設定した目標に対して予算を消費しきれない可能性があります。
配信の頻度や予算超過の可能性によって、事前の予算を超えない場合があるので注意しましょう。
例えば、ROAS目標(広告費用対効果)は予算金額の消化が保証されていないため、予算が余る可能性があります。
予算をなるべく使い切りたい場合は、最大数量を設定することがおすすめです。
データを集めるのに一定の期間が必要になる
入札戦略を設定したとしても、すぐに最適な配信が実施されるわけではありません。
1〜2週間ほどの期間はCPAやコンバージョンなどのデータを収集する必要があります。
データを集めている期間は配信の頻度や自動入札の精度が安定しない可能性があるので、事前に把握しておきましょう。
配信状況に一定期間のばらつきがあったとしても、データを取得できれば成果が見込めるため長期的な目線でみると、メリットが大きいです。
入札戦略は広告セットごとに設定できないの?
Facebook広告では、設定の階層が以下の3つに分かれています。
・広告セット
・広告
入札戦略はキャンペーンで設定を行うため、広告セットごとに細かい調整はできません。
広告セット別に予算の設定を実施したい場合は「広告セットの個別予算」から期間やエリアなどを変更します。
まとめ
いかがでしたか?
Facebook広告では、入札戦略を適切に設定して予算を管理することが大切です。
入札戦略は運用の手間や広告費の削減につながるメリットがあります。
ただし、予算を消費しきれなかったり、データ収集まで一定の時間が必要だったりするデメリットもあるので注意が必要です。
長期的な目線で考えると、機械学習を活用した配信によって最適化される方が利点が大きいです。
最大数量やバリュー最大化など、複数の選択項目があるため、特徴を捉えて目標に合ったものを選択しましょう。

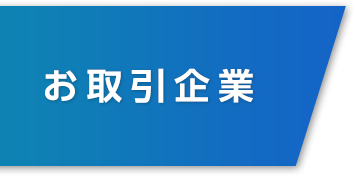





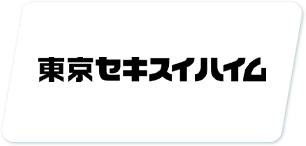
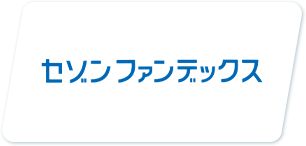











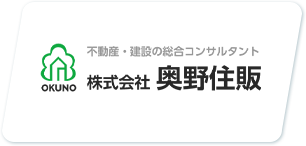




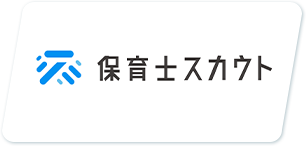



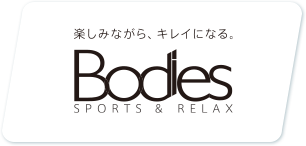


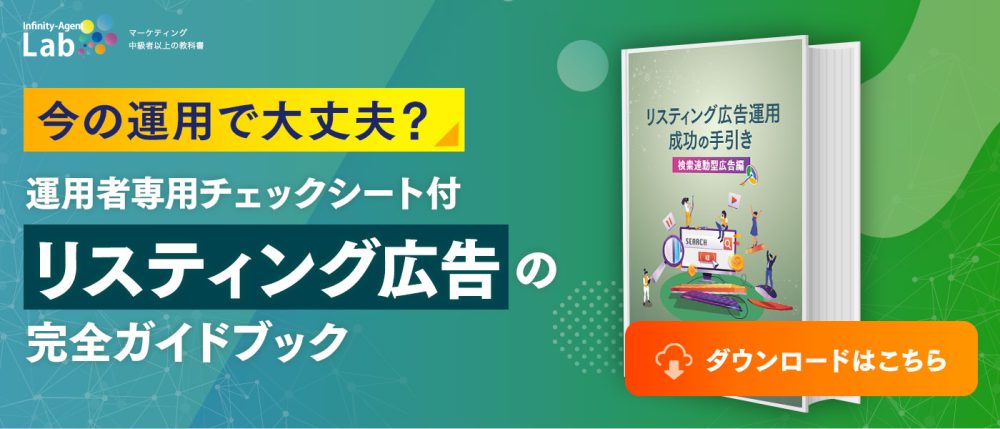

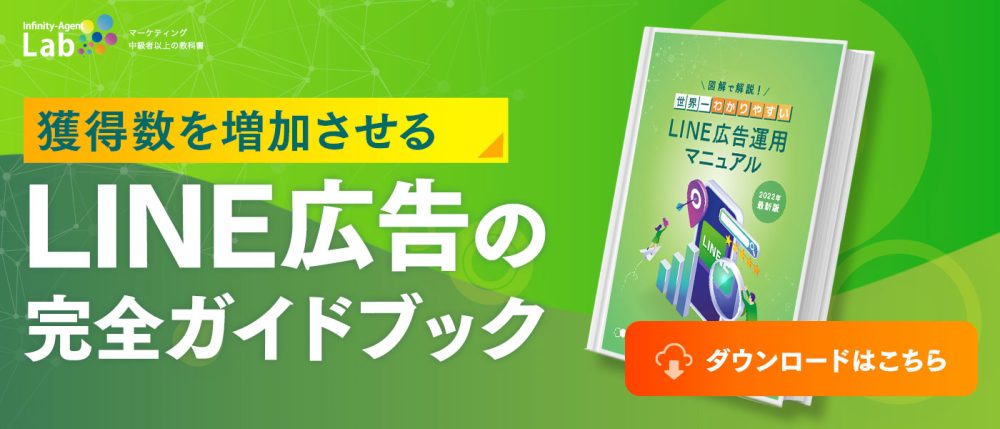
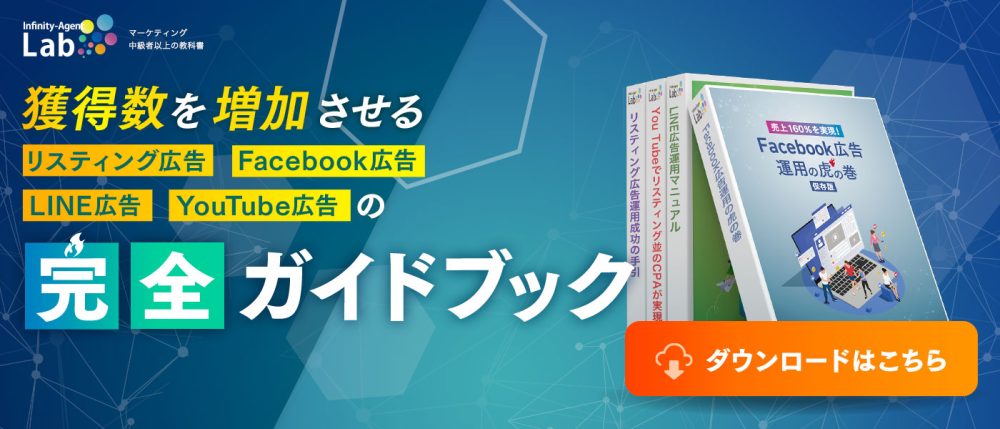








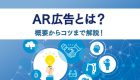











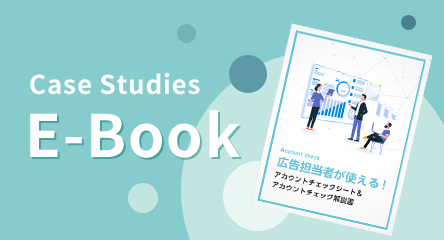 無料E-Bookダウンロード
無料E-Bookダウンロード アカウント無料診断
アカウント無料診断 お問い合わせ
お問い合わせ